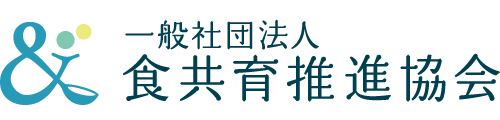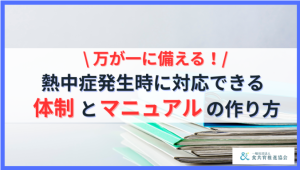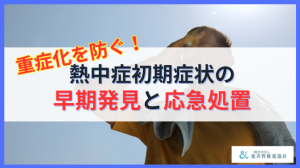建設・製造・警備…熱中症が多発する職場で今すぐできる5つの予防策
熱中症による労働災害は、屋外作業や高温多湿の現場で繰り返し発生しています。「起きやすい環境」であるほど、“標準的な対策”では足りない―これは管理者にとって避けて通れない現実です。
本記事では、熱中症が多発しやすい建設・製造・警備といった現場で、即実行できる5つの実践的な予防策を具体的にご紹介します。
水分補給ルールを徹底
“のどの渇き”を感じる前にすでに脱水が始まっている場合が少なくありません。
作業者任せにせず、15〜20分に1回の水分補給を業務の一部として制度化しましょう。
- 朝礼や休憩時間とは別に、「定時給水時間」を設ける
- 水・スポーツドリンク・経口補水液などを状況別に使い分ける
- 補給用の飲料を冷やして常備(5〜15℃が吸収効率に最適)
特にWBGTが28℃を超える環境では、自発的な水分補給に頼らない仕組み化が求められます。
「暑さの見える化」WBGT計測と掲示で判断基準を明確に
現場の暑さを“気温”だけで判断していませんか?
WBGT(暑さ指数)は、湿度や輻射熱を含めた総合的な熱環境の指標です。これを活用することで、主観的判断によらず、作業制限や休憩判断を行えます。
- WBGT測定器を現場に常設し、数値をホワイトボード等で掲示
- WBGT別の対応表を作成
- 熱中症警戒アラートと連動し、前日から体制強化を準備
「今日は作業できるのか?」を、感覚ではなく数値で判断する体制が事故を防ぎます。
「冷やす環境」をつくる!休憩所と冷却資材の整備
高温環境下での作業では、作業中の水分補給だけでなく“身体を冷やす”環境の確保が不可欠です。
- 風通しの良い日陰やエアコン付きプレハブを「冷却休憩所」として確保
- 保冷剤、氷、冷却タオル、ネッククーラーなどを常備
- 保冷剤入りの「クールベスト」や空調服の導入も有効
作業の合間にこまめに身体を冷やすことで、身体への負荷を軽減し、熱中症のリスクを着実に下げる実効的な対策となります。
「気づき」を促す!初期症状チェックと声かけの習慣化
熱中症の多くは、“いつもと違う様子”への気づきから防げるものです。
- 朝礼や作業前ミーティングの中で、「注意すべき熱中症のサイン」(例:めまい・吐き気・ふらつき)を共有
- 「顔色が悪い」「ぼーっとしている」などの兆候があれば、即報告・休憩
- 巡回時に「体調どう?」と声かけする文化を定着させる
熱中症は個人ではなく、周囲が気づくことで守れる災害です。
「もしもの時に備える」応急処置マニュアルと訓練
どれだけ予防しても、発生ゼロは保証できません。
だからこそ、万が一に対応できる体制とマニュアル整備が不可欠です。
- 発見→通報→応急処置→搬送のフローを明文化
- マニュアルは図解付きで現場に掲示
年1回以上の応急処置訓練(冷却・通報・搬送)を実施
【熱中症発生時の対応フロー例】
「知っている」ではなく、「動ける」人を増やすことが、最悪の事態を防ぐ最後の手段となります。
命を守るのは、今すぐ始める“現場の一歩”
熱中症対策は、制度だけでは機能しません。実際に現場で「どう動くか」「どう守るか」が、命を守るカギになります。
今回ご紹介した5つの予防策―
「水分補給のルール化」「WBGTの数値管理」「冷却環境の整備」「初期症状への気づき」「対応マニュアルと訓練体制の構築」は、どれも現場の安全文化を育てる第一歩です。
すべてを一度に完璧にする必要はありません。まずは「今できること」から確実に実行し、小さな改善を積み重ねていくことが、結果として重大災害を防ぐ大きな備えになります。